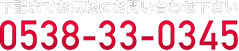塗装に影響を及ぼす外的要因
自動車の様々な使用環境の中においては、強固な結合を破壊して、塗装にダメージを
与えるような外的要因が多数存在します。その中にはカーディテーリング作業の範囲内で解決できるものから、復元が不可能な致命的なものまで様々です。
水
もっとも一般的と言える付着物ですが、これを完全に防ぐことは現在では難しいといえます。どんなに優れたコーティングなどを施していても物理的に発生してしまいます。
発生のメカニズム
降雨による雨水はもちろん、洗車時の水道水や井戸水など、様々な状況で日常的に発生します。塗装面に残った水滴が蒸発中にそこに含まれるカルシウムなどが凝縮され、水滴の外周に集まり白色のせき堆積物として残留することで発生します。
対応策
花粉
杉花粉の季節に特に多く見られる現象で、小さな点状のシミが無数に発生します。
発生のメカニズム
日本全国で春先になると大量のスギ花粉が森林等から風に乗って飛散します。
付着した花粉は水を含むと殻が破けてペクチンという酸性の多糖物質が出てきます。
このペクチンが乾燥して凝縮し、塗装を一緒に変形させてしまいます。
対応策
塗装を赤外線乾燥機などで加熱する事で塗装の中の応力を利用して塗膜を復元します。復元しても残っているシミはコンパウンドで研磨して仕上げます。
鳥糞
様々な種類の鳥が落とした糞が塗装面に付着し、塗膜を膨潤させ割れや剥がれが発生します。
発生のメカニズム
糞に含まれる有機酸が塗膜に浸透して膨潤させるのと同時に塗装の架橋結合を切断し、紫外線や温度変化、水分などで塗膜が割れたりはがれたりします。
対応策
基本的には付着後、速やかに除去することが大切です。膨潤のみの段階では、加熱する事で塗膜の中に浸透した水分、有機酸を蒸発させることで復元できる場合があります。割れや剥がれが有る場合には再塗装する必要があります。
黄砂
酸性雨
大気汚染等によって発生する酸性雨が塗装面に残留する事で塗膜に凹みを発生させます。水が溜まりやすい水平面に主に発生します。
発生のメカニズム
水と同様に雨水が塗装面に残留し蒸発することで、その中の酸性成分が濃縮され、塗装の架橋結合を切断してしまいます。結合が解かれたことで塗膜が溶解して、その部分が凹んでシミとなって目に見えるダメージとなります。
対応策
基本的に研磨して除去する方法になります。ダメージの度合いに応じてペーパーでの研磨が必要になり、あまり深追いしても塗膜を削り過ぎてしまうので、研磨作業前に適切な判断が必要です。
鉄粉
ブレーキダストや工事、鉄道、鉄工所等さまざまなところから発生する鉄粉が、その周辺を走行したり、駐車している際に飛散して塗膜に付着します。
発生のメカニズム
付着した鉄粉が参加して錆びる事で徐々に塗膜に食い込んでいきます。
対応策
ボディ用粘土もしくはアイアンカット、TG-1000Zなどの鉄粉除去剤を使用して除去します。軽度のものは除去剤のみで除去できる場合も有りますが、鉄粉除去剤は鉄粉が酸化して錆びた部分のみに反応するため、重度の場合には、除去剤の使用後に粘土を用いて再度除去する必要があります。
鉄粉除去剤と塗装
従来はアイアンカット等の鉄粉除去剤は中性で安全性が高く、新車の塗装を侵すような成分ではありませんが、特定の車種の特定のボディカラーにおいて、鉄粉除去剤を使用することで塗膜に除去できないムラが発生してしまう事例が報告されています。
例として国産小型車の特定のイエローが挙げられます。このカラーはメタリックは使用していませんが、通常のイエローカラーの塗装とは異なり、深みのある鮮やかなイエローを引き出すためにトップコートのクリアー塗装に若干の黄色系顔料が添加されています。
明確な原因はメーカーでも明らかにしていませんが、黄色系の顔料には酸化鉄が使用されている場合があり、この顔料の成分と鉄粉除去剤との何らかの化学反応が起きる事で塗装にムラを発生させてしまうのではないかと考えられます。
この状態は塗装表面ではなく内部まで及ぶため、研磨では復元できませんので再塗装が必要となってしまいます。
鉄粉除去剤をご使用の際にはこの点を考慮した上で作業を行いましょう。
架橋密度と研磨性
前述の通り研磨の対象としているトップコートの塗装はいずれの場合も架橋結合で樹脂が結ばれておりそれを研磨で削り取っていくことになります。
ここで問題になるのは研磨時によく言われる「硬さ」と言うことになります。
一般的な塗装の硬さは1〜3H程度ですが、これは架橋密度によって異なり、それが研磨性に関連してきます。